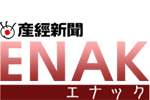毎年1巻ペース「なぜローマは繁栄したのか」
塩野七生さん「ローマ人の物語」完結 15年かけ
東京朝刊 by 桑原聡
イタリア在住の作家、塩野七生さん(69)の「ローマ人の物語」(新潮社)がついに完結、あす15日に最終巻(第15巻)「ローマ世界の終焉」が発売される。
平成4年、第1巻「ローマは一日にして成らず」の刊行にあたって、《1年に1冊のペースで刊行し、15年で完結する》と“公約”した塩野さんは、この15年間、「ローマ人の物語」に専念、1年の半分を史料の精読、半分を執筆にあて、約束通りゴールにたどり着いた。
「自分の羽根を一本一本抜きながら美しい織物を織り上げていった『夕鶴』のつうのよう。丸裸になった気分がします。しばらく休んで羽根を生やさなければオーブンに入れられそう」と塩野さん。
ローマの歴史といえば、英国人史家ギボン(1737〜94年)の「ローマ帝国衰亡史」全6巻が著名だが、同書が扱うのはローマ全盛期の5賢帝の時代(96〜180年)から、1453年の東ローマ帝国滅亡までで、ローマの興隆期は描かれていない。
これに対して塩野さんは《なぜローマのみが民族、文化、宗教の違いを超えた普遍帝国を実現しえたのか》という問題意識を持って、前753年のローマ建国から476年の西ローマ帝国滅亡までを描き切った。
《人間とは善悪を併せ持つ存在である》との冷徹な認識に貫かれた塩野さんの叙述は、多くの読者の心をつかみ、単行本14巻の累計発行部数は約220万部、文庫28冊(単行本の10巻まで)は約540万部と、この種の本としては異例の数字を記録している。
人類の歴史のなかで、なぜローマのみが、民族、文化、宗教の違いを超えた《普遍帝国》を作り上げることができたのか−。
「だれも私の疑問に答えてくれなかった。だから自分で答えを探そうとしたのです」
納得のゆく答えを出すのに15年の歳月と15巻のボリュームが必要だった。
「手っ取り早く分かりやすいということが、それほど大切なことだとは思いません。歴史とは人間がつくるもの、人間そのもの。複雑な人間の営為を簡単に書くことなど私にはできません。私は叙述は好きですが、解説は大嫌いなんです」
塩野さんの視線は、イタリア・ルネサンス期の思想家で「君主論」の著者、マキャベリ(1469〜1527年)に通じる。
「ルネサンスとは、1000年もの間キリスト教に導かれてきたが、欧州人の人間性はちっとも向上しないではないか、という問題意識から起こったものです。そこでルネサンス期の人々が注目したのがキリスト教以前の古代ギリシャと古代ローマだったのです。マキャベリは、宗教や哲学によって人間性は向上するものではない、と考えるローマ人のリアリズムに触れて《人間とは何か》を学び、善も悪も併せ持つという人間性の現実を直視したうえで、統治のあり方を考えるようになりました。私がマキャベリにひかれるのは、彼が人間に対してリアリズムに徹したまなざしを持っているからです」
ローマは、伝統的に異民族に対して寛容政策をとり、常に制度の見直しを怠らなかった。それは、古代ローマが多神教世界であったことと結びついている。
「キリスト教は、まず天国ありきで、この世は仮の世という認識です。それじゃあ本気でこの世をよくしようとは思わないでしょう。多神教のローマでは、死者の国はありますが、それは天国ではありません。それゆえ、いま生きている世界をよりよくしようという強い意志が生まれたのだと思います。ローマ人は人間という複雑な存在をしっかと見据えたうえで制度を作り出し、メンテナンスと見直しを怠りませんでした」
ところで、キリスト教徒ではない日本人というポジションは叙述にどんな影響を与えたのだろう。
「ものを書くとき、自分が日本人だと意識したことはありません。しかし、欧州の史家がローマ史を書こうとすれば、どうしても共和制を高く、帝政を低く評価してしまうでしょう。まったく別の文明圏に生まれ育った私は、クールに描くことができたと思います。私は政治とは結果だと考えます。その視点から見れば、帝政が悪いものだとはいえないし、キリスト教に対しても敵ながらあっぱれと思うことは多いですよ。こういう視点は、欧州の史家にはないかもしれませんね」
西欧的価値観が壁に突き当たっているいま、「ローマ人の物語」は輝きをいっそう増す。なぜなら「共生」の手がかりがここにあるからだ。
 |
| 「ローマ人の物語」に込めた思いを語る塩野七生さん |
平成4年、第1巻「ローマは一日にして成らず」の刊行にあたって、《1年に1冊のペースで刊行し、15年で完結する》と“公約”した塩野さんは、この15年間、「ローマ人の物語」に専念、1年の半分を史料の精読、半分を執筆にあて、約束通りゴールにたどり着いた。
「自分の羽根を一本一本抜きながら美しい織物を織り上げていった『夕鶴』のつうのよう。丸裸になった気分がします。しばらく休んで羽根を生やさなければオーブンに入れられそう」と塩野さん。
ローマの歴史といえば、英国人史家ギボン(1737〜94年)の「ローマ帝国衰亡史」全6巻が著名だが、同書が扱うのはローマ全盛期の5賢帝の時代(96〜180年)から、1453年の東ローマ帝国滅亡までで、ローマの興隆期は描かれていない。
これに対して塩野さんは《なぜローマのみが民族、文化、宗教の違いを超えた普遍帝国を実現しえたのか》という問題意識を持って、前753年のローマ建国から476年の西ローマ帝国滅亡までを描き切った。
《人間とは善悪を併せ持つ存在である》との冷徹な認識に貫かれた塩野さんの叙述は、多くの読者の心をつかみ、単行本14巻の累計発行部数は約220万部、文庫28冊(単行本の10巻まで)は約540万部と、この種の本としては異例の数字を記録している。
塩野七生に聞く
「クールな視点で描けた」
ローマ建国から西ローマ滅亡までを描き切った作家、塩野七生さんの出発点は、素朴な疑問だった。
「クールな視点で描けた」
人類の歴史のなかで、なぜローマのみが、民族、文化、宗教の違いを超えた《普遍帝国》を作り上げることができたのか−。
「だれも私の疑問に答えてくれなかった。だから自分で答えを探そうとしたのです」
納得のゆく答えを出すのに15年の歳月と15巻のボリュームが必要だった。
「手っ取り早く分かりやすいということが、それほど大切なことだとは思いません。歴史とは人間がつくるもの、人間そのもの。複雑な人間の営為を簡単に書くことなど私にはできません。私は叙述は好きですが、解説は大嫌いなんです」
塩野さんの視線は、イタリア・ルネサンス期の思想家で「君主論」の著者、マキャベリ(1469〜1527年)に通じる。
「ルネサンスとは、1000年もの間キリスト教に導かれてきたが、欧州人の人間性はちっとも向上しないではないか、という問題意識から起こったものです。そこでルネサンス期の人々が注目したのがキリスト教以前の古代ギリシャと古代ローマだったのです。マキャベリは、宗教や哲学によって人間性は向上するものではない、と考えるローマ人のリアリズムに触れて《人間とは何か》を学び、善も悪も併せ持つという人間性の現実を直視したうえで、統治のあり方を考えるようになりました。私がマキャベリにひかれるのは、彼が人間に対してリアリズムに徹したまなざしを持っているからです」
ローマは、伝統的に異民族に対して寛容政策をとり、常に制度の見直しを怠らなかった。それは、古代ローマが多神教世界であったことと結びついている。
「キリスト教は、まず天国ありきで、この世は仮の世という認識です。それじゃあ本気でこの世をよくしようとは思わないでしょう。多神教のローマでは、死者の国はありますが、それは天国ではありません。それゆえ、いま生きている世界をよりよくしようという強い意志が生まれたのだと思います。ローマ人は人間という複雑な存在をしっかと見据えたうえで制度を作り出し、メンテナンスと見直しを怠りませんでした」
ところで、キリスト教徒ではない日本人というポジションは叙述にどんな影響を与えたのだろう。
「ものを書くとき、自分が日本人だと意識したことはありません。しかし、欧州の史家がローマ史を書こうとすれば、どうしても共和制を高く、帝政を低く評価してしまうでしょう。まったく別の文明圏に生まれ育った私は、クールに描くことができたと思います。私は政治とは結果だと考えます。その視点から見れば、帝政が悪いものだとはいえないし、キリスト教に対しても敵ながらあっぱれと思うことは多いですよ。こういう視点は、欧州の史家にはないかもしれませんね」
西欧的価値観が壁に突き当たっているいま、「ローマ人の物語」は輝きをいっそう増す。なぜなら「共生」の手がかりがここにあるからだ。
産経Webは、産経新聞社から記事などのコンテンツ使用許諾を受けた(株)産経デジタルが運営しています。
すべての著作権は、産経新聞社に帰属します。(産業経済新聞社・産経・サンケイ)
(C)2006.The Sankei Shimbun All rights reserved.