 |
 |
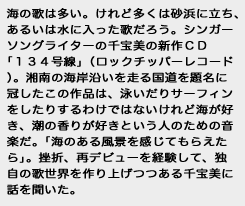 |
|
 |
|

千宝美 19歳ぐらいのときにミュージカル出演者の一般公募がありまして、踊られへんのに受かった。後から聞いたら歌で通ったと。そのとき自分が表現できるのは歌なんだと思ったのがきっかけでした。もちろん幼いころから音楽は大好きで、中森明菜さんが出るテレビ番組はカセットテープに録音して何度も聴き直したり。大阪に住んでいたころ知人の紹介でがバックコーラスの一員としてある方のライブのステージに立ったのが具体的な最初になります。
愛媛県に生まれた。父親の仕事の関係で山口に転居。高校入学と同時にこんどは大阪へと移った。
 −−シンガーソングライターというより歌い手になりたかったということ?
−−シンガーソングライターというより歌い手になりたかったということ?千宝美 幼いころは歌謡曲を聴いて育ちましたし、優先順位としては「うたうこと」のほうが上でした。曲を作ったのは21歳のときに米国のシンガーソングライター、キャロル・キングの有名なアルバム「つづれおり」を聴いて、こういう作品が作れたらいいなと思ったのがきっかけですから、ずつと後のことなんです。「つづれおり」は大阪のFMラジオでアルバイトをしていた際にいただいたもので、それまで技術でうたおうとしていた自分が間違っていたのではないかなどいろいろと考えさせられもしました。キャロル・キングは自分で曲を書いているんだ。こんな温度のある音楽があるんだと感動したんです。
−−もらったCDのアーティストがキャロルじゃなかったら、その後の音楽性も異なっていた?
千宝美 ほんとうにそうですね。
−−FM放送局でアルバイトしていたということですが
千宝美 ミュージカルに出たことで、ますますうたいたいと思い始めていたらところ「音楽に近いところで働いたらいい」とおっしゃってくれる方がいて、紹介していただいたんです。
−−アシスタントディレクターだったのに番組のパーソナリティーに抜擢されたとか
千宝美 はい。あるとき廊下を歩いていたらディレクターに声をかけられて原稿を渡されて、DJの方を相手に読んだら「はい、じゃあ来月からDJだからね」といわれて。びっくりしましたけれど、選ぶほうも選ぶほうですよね。大勢をオーディションしたあげく勢いで私を選んだんでしょうね。周りも驚いていましたけれど私もすごく大変でした。もちろんメーンパーソナリティーの方がいらっしゃるのですけど、生放送3時間のリクエスト番組でしたから。小学生のころから本を音読するのは好きでしたけれど突然、ADからDJですから。
FM放送との縁は深くデビュー後にパーソナリティーになった番組のうち「太陽石油プレゼンツ『千宝美のナチュラルブリーズ』」(FM愛媛毎週土曜11:00-11:55放送)は、ことしで6年目に入る。そもそもデビューのきっかけも、FM放送だった。
−−そのままラジオのパーソナリティーになろうとは考えなかったの?
千宝美 続けるつもりはないと周りも気づいていたんでしょうね。番組を始めて3カ月たったときディレクターの方に「これからどうしたいの?」と尋ねられて「やっぱり、うたいたいです」と。すると「ほんなら君、東京いったらいいねん」って。若かったし私も真に受けて半年バイトを続けて東京に出ました。若いってすごいなと思います。21歳になってすぐでした。あのとき、軽い調子でいわれていなかったら東京には出なかったでしょうね。

−−上京して…
千宝美 まずライブする場所を探しました。東京にも何人か知り合いの方がいらして、くっついてライブを見にいったりコーラスの仕事をいただいたり。一方で新宿のライブハウスにデモテープを持ち込んでうたわせてもらうことになりました。そのころシンガーソングライター、松山千春さんのバックでアコースティックギターを弾いている丸山政幸(丸山ももたろう)さんにお会いする機会があって、すばらしい演奏で、私まだ何も知らなかったから「こんど東京でライブやるんですけど、私のバックでも弾いてください」とお願いしてしまって。そうしたら「いいよ、いいよ」とおっしやったから実際に電話したんですよ。「ライブ決まったから弾きにきてください」って。丸山さん「こいつ、本当に電話してきたぞ」って思ったでしょうけど、2年間ぐらいずっと演奏してくださったんですよ。
 −−ライブでは何をうたっていたの?
−−ライブでは何をうたっていたの?千宝美 オリジナル。もうオリジナルを作っていましたから。例の「つづれおり」を聴いた後から。東京出てくるちょっと前からですね。
−−つまり、作りはじめたばかりの曲を、いきなりお客さんに聴かせてしまったということですね?
千宝美 ほんとうですね、いま思ったらすごい! 丸山さんからもやっぱり「何うたうねん?」って聞かれましたっけ。「いやあ、オリジナルです」って答えました。当時の私は譜面すらかけなかったのに。自己流の“なんちゃって譜面”を丸山さんにお見せして「テンポはこれぐらい。リズムはこんな感じ。ここから弾いてもらえますか」。「こうか?」って丸山さんが弾いて、私がうたう。「ああ、分かった、分かった」。そんな感じでライブの準備はしていたんですよ。
−−丸山さんっていい方ですねえ
千宝美 ほんとうに! 「ここのコード(和音)は、こっちのほうがええんちゃうか?」「あ、そうですね」という具合に、私もだんだん曲作りが分かってきて、なんちゃって譜面も少しは譜面らしくなってきて。ライブは1カ月に1回でしたけれど毎回新しい曲を聴かせたくて、どんどん作りました。丸山さんは「おいおい、覚えられへんでえ。ようまあ、こんなにな作ってくんね」と。そんな感じでしたねえ。
上京から3年後、1人の女性作曲家、との出会いが、運命を大きく変える。森たまき。
−−森さんとの出会いは?
千宝美 「冬の匂いが消える頃」を聴いて衝撃を受けたんです。それまで自作自演というスタイルにこだわっていたけれど「冬の匂いが消える頃」には、他人の作品なのに共感できた。それやったら自分で書かなくても「うたいたい」と思った歌ならうたってもええんちゃうかな。それで森さんに「うたいたい」と伝えました。考えたらもともとはうたいたかっただけなのに曲を書き始めたら「絶対に自分の曲で」と思い始めていた。うたいたいと思える歌と出合ったことで「あ、私は歌をうたいたかったんや」というところに戻れることができた。なかなかうたいきれない自分がいて、思いのほか大変でしたけど。
−−「冬の匂いが消える頃」のどんなところに共感を?
千宝美 たまたま当時の自分をめぐる状況と重なって。
−−ということは、単にタイミングがよかっただけなのでは?
千宝美 いえ、楽曲のもつパワーみたいなものがあったのだと、やっぱり思います。シンプルなんですよね。よい曲はなんだかんだしなくてもいいのだということを学びましたし、歌詞が(耳に)飛び込んでくるということがあるのだということも知りました。
−−とすると大転換になった?
千宝美 異常に自作曲にこだわりながらも、じゃあ歌唱についてはどうなのかと考えていた時期だったんでしょう。「冬の匂いが消える頃」を吹き込んだデモテープをアルバイトしていた大阪のFM放送局にもっていったら快くオンエアしてくださって、そうしたら聴取者からファクスがたくさん送られてきたんです。とても感動しました。「車を停めて聴き入った」とか前向きなメッセージがたくさんあって。今でもそのファクスは保存しています。

−−活動を休止しているときは何を考え、どう過ごしていたのですか?
千宝美 アルバイトとかしていました。ふつうに朝起きて働いて…という生活を。テレビを観てほかの人がうたっているのを観るのもいやだし、CDを聴くのもいやでした。でも、次第に、じゃあほかにやりたいことはあるのかと自問するようになりました。音楽を休んだら何があるかといったら何もない。やっぱり音楽しかない。
−−立ち直るまでにどのぐらいの時間かかったのですか?
千宝美 どうだろう…1年ぐらいかな。ミニアルバム「unbalance」を作る半年前ぐらいにふっきれたところがあって。「いいや」と思ったんですよ。ちょっと開き直りといいますか。何かを失ったとしても、私自身は変わらないのではないかと光が見えてきたんですよ。
−−ひょっこり?
千宝美 ひょっこりですね。少しずつ気持ちは上向いていたんでしょうけど、ある日「あ、もう大丈夫」って。
2003年12月、本格的に活動を再開。04年4月には、約2年ぶりとなるCD、ミニアルバムの「unbalance」(1st mini album)を発売する。「冬の匂いが消える頃」の再録音をのぞけばすべて自作曲で固めた。
−−「unbalance」を振り返ると?
千宝美 スタッフの方たちが、すべての作業を私と一緒にやってくださった。選択を私に委ねて。いい経験になりました。ほんとうにスタートできるという感じでした。あれが最初だったんですよね、自分の作詞作曲が形になったの。あ、こんなにうれしいんだって思いました。
−−再び自作にこだわりを?
千宝美 もう、そんなにこだわっていません。うたいたいと思う歌があればチャレンジしたい。

千宝美 去年ぐらいから疲れたら湘南の海に行くようになったんです。小さいころ愛媛で育っていたので海は周りにあったのに、こっちに来てからぜんぜん海にいかなくなって。私はサーフィンをするわけでもないし。空気が違うし、私、潮のにおいが好きなんですよね。幼いころの記憶に重なるというか。愛媛で暮らしていたころ、大阪の祖父母を訪ねるため深夜のフェリーに乗って大阪から松山まで行っていました。子供だった私にとって夜更かしができる楽しみやったんです。そのときの記憶と潮のにおいがいつも一緒。潮のにおいを感じると、ワクワクしたりキュンとしたり。
−−なるほど
千宝美 次第に湘南でうたうことも増えて。音楽をほんとうに楽しんいる人たちが多い場所。そういう姿を見て、音楽ってそうだなって感じさせてくれたり。海の中に入るわけじゃなくて、海がある風景が好き。それを描ければいいなあと思って作りました。愛媛の海は思い出すには遠い。今の私にとっての海は134号線沿いなんです。
−−つまり、海を描こうと思った
千宝美 いえ、海のある風景、ですね。
−−「夏の雪」という歌は、しかしホタルの歌ですが?
千宝美 葉山にホタルが住んでいる場所があるって聞いて。これはいちばん情熱的で熱い曲。物事がうまくいかないと人のせいにしてしまったり、そういうことってだれにでもあると思うのですけど、結局は自分の人生。自分が輝かないいけない。そういう内容で、これは私自身に言ってもいる。そういう歌です。
 −−なるほど
−−なるほど千宝美 いろんな海があると思うんです。いまサーフミュージックが流行していますが、彼らは海にジャバジャバ入っていくイメージがある。私は海で泳ぐわけでもなく、海を見ているのが好き。海にいる人たちの風景が好きだったりするだけなので、聴く人がどういう反応をするのか気になりましたけれど、私だけじゃなく、きっとそういう人って大勢いると思うんですよ。サーフィンしないけど海はすごく好きという人たちが。そういうにおいがするアルバムにはなったんじゃないかと思っています。
−−湘南というと湘南サウンドという言葉を思い出すけれど、あれは海の中に入る人たちの歌で、こちらは海岸線の道路から潮の香りを感じたりすると
千宝美 私がむっちゃ真っ黒でサーフィンやっている人だったらまた違う音楽になっていたのでしょうけど、泳がないけど海が好きという人はきっとたくさんいるんじゃないでしょうか。私も愛媛では自転車をこいで空港の裏の海へ潮のにいおいをかぎにいったりしていました。そういうことを思い出したら、私の好きな海、私らしい海の音ができればいいなと思ったんです。
−−なるほど
千宝美 134号線というタイトルなので地域が限定されているように思われるでしょうけど、私は愛媛の海を思ったわけですし、海岸線沿いの道路はいろんな街にあります。聴く人それぞれの海岸線を思い描いて聴いてもらえたらいいなと思います。

134号線
Rock Chipper
OWCR-2021
¥1,800(Tax in)
1 一色海岸
2 夏の雪
3 光の花束
4 太陽の季節
5 鳳仙花
6 奇跡
●Profile
ちほみ 千の美しい宝が持てるように- と祖父が名付けた。
愛媛県に生まれ、父親の仕事の関係で山口で、高校入学と同時に大阪へと移る。卒業後、知人からの紹介でラジオCMの歌唱や、バックコーラスなどの“歌う”仕事を始め、少しでも音楽業界に近い環境でと、在阪放送局(fm osaka,MBS,FM CO・CO・LOなど)でアルバイトを始める。
1997年春、プロのシンガーを目指し、単身上京。上京から3年後、一人の女性コンポーザー(森たまき)との出会いが、運命を変える。
2001年1月、森たまきの描く珠玉の名作「冬の匂いが消える頃」でデビュー。同年9月には2作目のシングル「見つめていたくて」を発売。
活動を休止。2003年12月より、本格的に活動を再開。04年4月にミニアルバム「unbalance」を発売。
Rock Chipper
OWCR-2021
¥1,800(Tax in)
1 一色海岸
2 夏の雪
3 光の花束
4 太陽の季節
5 鳳仙花
6 奇跡
●Profile
ちほみ 千の美しい宝が持てるように- と祖父が名付けた。
愛媛県に生まれ、父親の仕事の関係で山口で、高校入学と同時に大阪へと移る。卒業後、知人からの紹介でラジオCMの歌唱や、バックコーラスなどの“歌う”仕事を始め、少しでも音楽業界に近い環境でと、在阪放送局(fm osaka,MBS,FM CO・CO・LOなど)でアルバイトを始める。
1997年春、プロのシンガーを目指し、単身上京。上京から3年後、一人の女性コンポーザー(森たまき)との出会いが、運命を変える。
2001年1月、森たまきの描く珠玉の名作「冬の匂いが消える頃」でデビュー。同年9月には2作目のシングル「見つめていたくて」を発売。
活動を休止。2003年12月より、本格的に活動を再開。04年4月にミニアルバム「unbalance」を発売。

