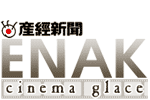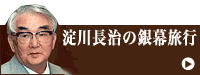妻夫木聡主演 「時代」を表現する職人力
映画「憑神」の舞台裏をリポート!
大阪夕刊 by 福本剛
下級武士が3人の災いの神にとりつかれてしまう映画「憑神」。「鉄道員(ぽっぽや)」で組んだ作家の浅田次郎と降旗康男監督が再びタッグ、妻夫木聡、西田敏行らを配して幕末の武士らの人生模様を描いた注目作だ。時代劇の中枢、東映京都撮影所の技術も結集した同作品。同所を訪れ、撮影の裏側をのぞいた。
武士のまげ、女性の後ろ髪、子供のおさげ…。時代劇の特徴が最も出るのが、かつらだ。メークの大村弘二さん(41)は「一番時代劇らしいが、最も難しい部分」ともいう。武士や商人、奉行、町娘など、一人ひとりの表情や背景が違う。かつらも、一つひとつが違うのだ。
幕末から明治をたどる主人公の武士、彦四郎(妻夫木)には、時代や状況に応じて3パターンのかつらが用意された。大村さんは「形がきれいで、やりやすい頭だった」と笑う。幕末を意識し、まげが主張しないソフトなかつらを心掛けたとも。
「個人の性格、職業、立場、時代…。作品から読み取れるすべての情報が、かつらのヒントになる」−かつらを見れば、人物が分かるのだ。
ふすまに手あかをまぶし、木を焼いて年輪を感じさせる工夫も。塗装や汚しを手掛けた美術の池端松夫さん(59)は「木目を浮き出し、ふすまや障子の引き手のこすれ具合にもこだわった。でも、照明や人の影で違ってくるから、何回やっても難しい」と笑う。
劇中に登場する手紙やあんどん、店の看板の文字も、時代に合わせて書いたものだ。デザインを担当した背景の宇野龍之介さん(71)は「あまり崩してもいけない。ちゃんと読める字で、しかも時代を感じさせないと…」と苦労を語る。
宇野さんの仕事場には、各時代の文献や、文字の書かれた絵、看板、手紙の記録がずらり。これらを元に、劇中のさまざまな“時代文字”が作られていたのだ。
災いの神にとりつかれた彦四郎の奮闘を軸に、江戸庶民の生活がコミカルに描かれる同映画。妻夫木らの演技や、降旗の演出はもちろん、撮影現場の陰の努力も知ることで、より時代劇映画への理解も深まるはずだ。23日から大阪・梅田ブルク7などで公開。
かつらが語る人物像
 |
| 頭の形などに合わせ、かつらを作り上げていく大村さん |
幕末から明治をたどる主人公の武士、彦四郎(妻夫木)には、時代や状況に応じて3パターンのかつらが用意された。大村さんは「形がきれいで、やりやすい頭だった」と笑う。幕末を意識し、まげが主張しないソフトなかつらを心掛けたとも。
「個人の性格、職業、立場、時代…。作品から読み取れるすべての情報が、かつらのヒントになる」−かつらを見れば、人物が分かるのだ。
生活のにおい
撮影所内に建つ立派な建物。彦四郎が居候する別所家だ。オープンセットとはいえ、8畳間、6畳間、台所、離れなど本格的な屋敷そのもの。美術の松宮敏之さん(48)は「単なる江戸時代の家ではない。武士らが行き来する生活のにおいがし、いろいろな神も出てきそうなイメージもふくらませた」
 |
| 映画「憑神」で、災いの神(森迫永依、左)にとりつかれる彦四郎(妻夫木聡)=(C)2007「憑神」製作委員会 |
ふすまに手あかをまぶし、木を焼いて年輪を感じさせる工夫も。塗装や汚しを手掛けた美術の池端松夫さん(59)は「木目を浮き出し、ふすまや障子の引き手のこすれ具合にもこだわった。でも、照明や人の影で違ってくるから、何回やっても難しい」と笑う。
時代文字の秘密
 |
| 江戸時代の屋敷のセットの苦労を語る松宮さん |
宇野さんの仕事場には、各時代の文献や、文字の書かれた絵、看板、手紙の記録がずらり。これらを元に、劇中のさまざまな“時代文字”が作られていたのだ。
災いの神にとりつかれた彦四郎の奮闘を軸に、江戸庶民の生活がコミカルに描かれる同映画。妻夫木らの演技や、降旗の演出はもちろん、撮影現場の陰の努力も知ることで、より時代劇映画への理解も深まるはずだ。23日から大阪・梅田ブルク7などで公開。
産経Webは、産経新聞社から記事などのコンテンツ使用許諾を受けた(株)産経デジタルが運営しています。
すべての著作権は、産経新聞社に帰属します。(産業経済新聞社・産経・サンケイ)
2007(C)SANKEI DIGITAL INC. All rights reserved.