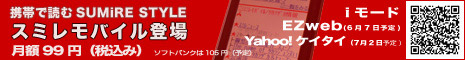産科・歯科連携の広がりに期待
妊婦さんも歯が命 口腔ケアで出産時のリスク軽減
2008/2/27 産経新聞
東京朝刊 by 平沢裕子
歯周疾患が早産・低体重児出産のリスクを高めることが米国で報告されて約10年になる。しかし、産科医・歯科医とも認識が十分でなく、妊婦への口腔(こうくう)ケアの取り組みはまだ十分とはいえない。妊娠中の口腔ケア指導は、出産時のリスクを減らすだけでなく、子供の虫歯予防にもつながることが分かっており、産科・歯科連携の広がりが期待されている。
妊娠に伴う食生活の変化やつわりで歯磨きがうまくできないなど、妊娠中は口腔内トラブルを起こしやすい状況にある。
一方で歯科医師側も「妊婦に麻酔を使ってもいいのか」など妊婦の治療に不安を抱く場合が少なくない。
宮川医院産婦人科(神奈川県藤沢市)では、口腔ケアの重要性を知らせるパンフレットを配布したり、口腔内トラブルのある患者に歯科医を紹介するなど、歯科との連携を積極的に行っている。
宮川智幸院長は「赤ちゃんの乳歯は妊娠中につくられる。口腔ケアの指導を妊婦さんにすることは、早産のリスクを減らすだけでなく、赤ちゃんの歯の健康にもつながる」と話す。
歯科治療が大事といっても、妊娠初期は流産の危険性や薬剤の影響も心配だ。宮川院長は「妊娠初期にたえられない症状があるときは応急処置のみをしてもらい、きちんとした治療は安定期に入ってから行った方がいい。歯科受診の際は、必ず妊娠していることを知らせ、治療のときに楽な体位で短時間ですむよう歯科医に頼むように」とアドバイスする。
産科と歯科の連携で、乳幼児の虫歯予防に効果を上げているところもある。
年間出生数1000人の産婦人科医院に併設するハロー歯科(岡山市)では、妊婦健診と同時期に妊婦歯科健診を実施し、治療やカウンセリングなどを行っている。また出産後も、母子の定期的な歯科健診を通して口腔ケアを指導している。
歯科疾患実態調査によると、3歳の虫歯経験者率は24・4%だが、同歯科の定期健診継続受診者は3・5歳で13・8%と全国平均の約半分だった。滝川雅之院長は「妊娠中の適切な口腔ケアは、丈夫な赤ちゃんの出産や子供の虫歯予防につながる。また子供の定期健診は予防が中心なので痛くなく、歯科恐怖も予防できる」と話す。
虫歯の原因となるミュータンス菌は、もともと赤ちゃんの口腔内にはおらず、家族、中でも母親の唾液(だえき)を介してうつることが多い。食べ物を噛み与えたり、スプーンを共有することが大きな要因になっている。
滝川院長は「口腔ケア習慣は母から子に伝達される。子供の歯を守るためにも、妊娠中からしっかりと口腔ケアに取り組んでほしい」と呼びかけている。
また「母乳は子供が虫歯になりやすい」と考えている人も多く、母子健康手帳に「歯のためには母乳は1歳のお誕生日ごろを目安にやめましょう」と記述があるものもある。宮川院長は「虫歯になるのは口腔ケアをちゃんとしないから。母乳かどうかは関係ない。寝る前に母乳を飲ませたら歯磨きをする習慣をつけてほしい」と話している。
 |
| 産婦人科クリニックを訪れ、歯科回診する滝川雅之院長=岡山市 |
妊娠に伴う食生活の変化やつわりで歯磨きがうまくできないなど、妊娠中は口腔内トラブルを起こしやすい状況にある。
一方で歯科医師側も「妊婦に麻酔を使ってもいいのか」など妊婦の治療に不安を抱く場合が少なくない。
宮川医院産婦人科(神奈川県藤沢市)では、口腔ケアの重要性を知らせるパンフレットを配布したり、口腔内トラブルのある患者に歯科医を紹介するなど、歯科との連携を積極的に行っている。
宮川智幸院長は「赤ちゃんの乳歯は妊娠中につくられる。口腔ケアの指導を妊婦さんにすることは、早産のリスクを減らすだけでなく、赤ちゃんの歯の健康にもつながる」と話す。
歯科治療が大事といっても、妊娠初期は流産の危険性や薬剤の影響も心配だ。宮川院長は「妊娠初期にたえられない症状があるときは応急処置のみをしてもらい、きちんとした治療は安定期に入ってから行った方がいい。歯科受診の際は、必ず妊娠していることを知らせ、治療のときに楽な体位で短時間ですむよう歯科医に頼むように」とアドバイスする。
産科と歯科の連携で、乳幼児の虫歯予防に効果を上げているところもある。
年間出生数1000人の産婦人科医院に併設するハロー歯科(岡山市)では、妊婦健診と同時期に妊婦歯科健診を実施し、治療やカウンセリングなどを行っている。また出産後も、母子の定期的な歯科健診を通して口腔ケアを指導している。
歯科疾患実態調査によると、3歳の虫歯経験者率は24・4%だが、同歯科の定期健診継続受診者は3・5歳で13・8%と全国平均の約半分だった。滝川雅之院長は「妊娠中の適切な口腔ケアは、丈夫な赤ちゃんの出産や子供の虫歯予防につながる。また子供の定期健診は予防が中心なので痛くなく、歯科恐怖も予防できる」と話す。
虫歯の原因となるミュータンス菌は、もともと赤ちゃんの口腔内にはおらず、家族、中でも母親の唾液(だえき)を介してうつることが多い。食べ物を噛み与えたり、スプーンを共有することが大きな要因になっている。
滝川院長は「口腔ケア習慣は母から子に伝達される。子供の歯を守るためにも、妊娠中からしっかりと口腔ケアに取り組んでほしい」と呼びかけている。
「妊娠したら歯が弱くなる」はウソ
「妊娠すると子供にカルシウムをとられて歯が弱くなる」と思っている人は多いのでは? サンスター歯科保健振興財団の主任歯科衛生士、高稲浩実さんは「いったん歯に蓄積されたカルシウムが再び体内に取り込まれることはないので、妊娠したから歯が弱くなるということはありません。ただ、つわりや育児で口腔ケアが十分できなくなり、妊娠・出産で虫歯となる人は多いようです」と話す。
また「母乳は子供が虫歯になりやすい」と考えている人も多く、母子健康手帳に「歯のためには母乳は1歳のお誕生日ごろを目安にやめましょう」と記述があるものもある。宮川院長は「虫歯になるのは口腔ケアをちゃんとしないから。母乳かどうかは関係ない。寝る前に母乳を飲ませたら歯磨きをする習慣をつけてほしい」と話している。
産経新聞社から記事などのコンテンツ使用許諾を受けた(株)産経デジタルが運営しています。
すべての著作権は、産経新聞社に帰属します。(産業経済新聞社・産経・サンケイ)
Copyright(C)2008 SANKEI DIGITAL INC. All rights reserved.