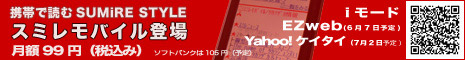専門店で魅力を探る
ご当地ギョーザに熱視線 国産+手作り=安心
2008/3/2 産経新聞
東京朝刊 by 榊聡美
中国製ギョーザ中毒事件の影響で、手作りする人が増えて皮やニラなどの材料が売り上げを伸ばす一方、全国の「ご当地ギョーザ(餃子)」が熱い注目を集めている。ギョーザはもはや日本の国民食。北海道から九州まで11店のご当地ギョーザ専門店が集まるフードテーマパークでその魅力を探った。
ナムコ・ナンジャタウン(東京都豊島区)にある「池袋餃子スタジアム」でこんな声が聞かれる。平日にもかかわらず、若いカップルや女性グループなどで込み合い、列をなす店もある。
ご当地ギョーザ=国産・手作りという安心感があるようで、「中毒事件が問題になってから、客足が前年比で2〜3割伸び、正直驚いています」と同スタジアム企画担当の溝口伸一さんは話す。
「ギョーザの街」で知られる宇都宮と浜松が味を競っているのもこの施設ならでは。
約80軒の専門店がある静岡県浜松市は、市が独自に調査したところ、一世帯当たりのギョーザの平均年間消費量が宇都宮市の約4倍にのぼり、昨年「ギョーザ消費量日本一」を宣言した。
浜松で50年以上の歴史をもつ老舗「石松」のギョーザは、まず円盤形の盛りつけが目をひく。そして、はし休めのゆでモヤシが“浜松風”の大きな特徴だ。
一方、宇都宮の「来らっせ」は宇都宮餃子会の12店が共同出店。こちらも不動の人気を誇る。
「風評被害? 問題ありませんよ」と同会の伊藤信夫代表。中毒事件発覚後、すぐに全加盟店を対象に原材料の調査を行い、その結果を受けて「安全宣言」を出した。
「地元では贈答用の需要が減っただけで、むしろお客さんは増えています。大丈夫、ギョーザには力があります」と、伊藤代表は胸を張る。
東京都北区の老舗「華興」のギョーザは、食べると甘みを含んだ肉汁がじゅわーっと口の中に広がる。甘みのもとはタマネギ。終戦後の物のない時代に安価だったタマネギをたっぷり使った伝統的レシピが引き継がれている。
「神龍(しぇんろん)」(札幌市)の「上富良野餃子」は、その名のとおり、皮の小麦粉をはじめ、野菜や豚肉、すべて上富良野産の素材を使用している。
また、とりわけ女性に人気が高い「四国丸亀 寺岡商店」(香川県)の「すだち餃子」は、たれでなく、四国の特産であるすだちを搾ってコショウをつけながら食べる。
スタイルも味わいもバラエティーに富んだご当地ギョーザに、「懐かしさを感じる」というファンは多い。「ご当地ギョーザは、画一的な味の冷凍ギョーザとは対極をなす存在です」と溝口さんは話している。
 |
| 個性豊かなご当地ギョーザの数々。手前から時計回りに「石松」「神龍」「四国丸亀 寺岡商店」「来らっせ」「華興」=東京「池袋餃子スタジアム」(緑川真美撮影) |
風評関係なし
「連日の“ギョーザ報道”で無性に食べたくなって」
ナムコ・ナンジャタウン(東京都豊島区)にある「池袋餃子スタジアム」でこんな声が聞かれる。平日にもかかわらず、若いカップルや女性グループなどで込み合い、列をなす店もある。
ご当地ギョーザ=国産・手作りという安心感があるようで、「中毒事件が問題になってから、客足が前年比で2〜3割伸び、正直驚いています」と同スタジアム企画担当の溝口伸一さんは話す。
「ギョーザの街」で知られる宇都宮と浜松が味を競っているのもこの施設ならでは。
約80軒の専門店がある静岡県浜松市は、市が独自に調査したところ、一世帯当たりのギョーザの平均年間消費量が宇都宮市の約4倍にのぼり、昨年「ギョーザ消費量日本一」を宣言した。
浜松で50年以上の歴史をもつ老舗「石松」のギョーザは、まず円盤形の盛りつけが目をひく。そして、はし休めのゆでモヤシが“浜松風”の大きな特徴だ。
一方、宇都宮の「来らっせ」は宇都宮餃子会の12店が共同出店。こちらも不動の人気を誇る。
「風評被害? 問題ありませんよ」と同会の伊藤信夫代表。中毒事件発覚後、すぐに全加盟店を対象に原材料の調査を行い、その結果を受けて「安全宣言」を出した。
「地元では贈答用の需要が減っただけで、むしろお客さんは増えています。大丈夫、ギョーザには力があります」と、伊藤代表は胸を張る。
個性派勢ぞろい
ご当地ギョーザは戦後、中国からの引き揚げ者が、見よう見まねで作ったのが始まりといわれる。身近な食材で作ることができ、栄養バランスにも優れた食べ物として人気を呼び、日本各地の風土や食文化に合ったギョーザが次々と生まれ、地域に根付いていった。
東京都北区の老舗「華興」のギョーザは、食べると甘みを含んだ肉汁がじゅわーっと口の中に広がる。甘みのもとはタマネギ。終戦後の物のない時代に安価だったタマネギをたっぷり使った伝統的レシピが引き継がれている。
「神龍(しぇんろん)」(札幌市)の「上富良野餃子」は、その名のとおり、皮の小麦粉をはじめ、野菜や豚肉、すべて上富良野産の素材を使用している。
また、とりわけ女性に人気が高い「四国丸亀 寺岡商店」(香川県)の「すだち餃子」は、たれでなく、四国の特産であるすだちを搾ってコショウをつけながら食べる。
スタイルも味わいもバラエティーに富んだご当地ギョーザに、「懐かしさを感じる」というファンは多い。「ご当地ギョーザは、画一的な味の冷凍ギョーザとは対極をなす存在です」と溝口さんは話している。
産経新聞社から記事などのコンテンツ使用許諾を受けた(株)産経デジタルが運営しています。
すべての著作権は、産経新聞社に帰属します。(産業経済新聞社・産経・サンケイ)
Copyright(C)2008 SANKEI DIGITAL INC. All rights reserved.