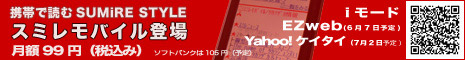児童書や実用書も
「お宝」見つかるか!?絶版前の本、半値で販売
2008/3/28 産経新聞
東京朝刊 by 海老沢類
書店で売れ残った絶版前の本を、定価の半値で販売するインターネットサイトが話題を呼んでいる。価格の維持を目的とした再販制度の弾力的な運用をアピールする試みの一つだが、これまでの期間限定セールとは異なり、1年を通して全国どこでも購入できるのが特徴だ。出版界が不況にさらされる中、高い返品率に悩む大手出版社も軒並み協力しており、倉庫に眠っていた本が息を吹き返すチャンスとして期待が寄せられている。
昭和図書の大竹靖夫社長は「『本が売れない』とひと口に言っても理由はさまざまで、値ごろ感があればもう1回勝負できる本もあるはず。魅力的な書き手が再発掘され、新たなファンが本屋に足を運ぶようになればうれしい」と話す。
昨年3月のスタート当初は一ツ橋グループ4社のみが本を提供していたが、10月以降は講談社や文芸春秋、筑摩書房など25社が系列を超えて参加。出品点数が5倍以上に増えたことで、もともと多かった児童書や実用書に加え、小説やノンフィクションの品ぞろえも充実してきた。大竹社長は「月100万円という販売目標には遠く及ばないが、リピーターは増えており、すでに30冊以上売れた児童書もある」と手応えを口にする。
書籍や雑誌は再販制度によって定価販売されている。これに対し、公正取引委員会は「消費者の利益を確保する」との理由から、業界に対して自由価格本の販売機会を広げるよう求めてきた。
こうした中、昭和図書では平成17年、東京・神田神保町に、絶版前の本などを半値で売る初の常設店「ブックハウス神保町」をオープン。今回のサイト開設と同様に、再販制度を弾力的に運用していることを積極的に打ち出すことで、制度そのものを死守する狙いがある。
また、大手出版社が系列を超えて値引きサイトに協力した背景には、高い返品率への危機感もある。出版科学研究所の調査によると、17年の書籍の返品率は38・7%。27〜30%程度で推移していた30年ほど前に比べ、増加が目立つ。昭和図書の大竹社長の推計では、年間約8億冊が返品され、うち2億冊が一度も読者の手に渡ることなく断裁処分されているという。販売部数が減る一方で新刊発行点数は年々増えており、返品率の上昇に拍車をかけているのが実態だ。
大竹社長は「ネットでの値引き販売は、在庫をいかにさばくかの方法を探る実証実験。著者のためにも、断裁処分を減らせるような流通システム作りにつなげていきたい」と話す。
出版業界は15年から、期間限定で自由価格本を販売する「謝恩価格本フェア」を開催している。10回目は4月23日〜6月23日、出版社112社が参加し、1473点の書籍が定価の5割引で販売される。詳細はバーゲンブック・jp(www.bargainbook.jp)。
 |
| 常設店「ブックハウス神保町」の売り場。在庫がわずかな本も値引き販売されている=東京都千代田区 |
大手出版社も賛同
サイトは小学館、集英社をはじめとする一ツ橋グループの物流を手がける昭和図書(東京)が運営する「ブックハウス神保町・com」(www.bh-jinbocho.com)。出品されている本は、書店から返品された約600点。在庫がわずかな希少本も含まれるが、雑誌やコミックは販売していない。すべて初版発売から1年以上が経過したもので、昭和図書が各出版社と交渉したうえで買い取り、定価の5割引で販売している。
昭和図書の大竹靖夫社長は「『本が売れない』とひと口に言っても理由はさまざまで、値ごろ感があればもう1回勝負できる本もあるはず。魅力的な書き手が再発掘され、新たなファンが本屋に足を運ぶようになればうれしい」と話す。
昨年3月のスタート当初は一ツ橋グループ4社のみが本を提供していたが、10月以降は講談社や文芸春秋、筑摩書房など25社が系列を超えて参加。出品点数が5倍以上に増えたことで、もともと多かった児童書や実用書に加え、小説やノンフィクションの品ぞろえも充実してきた。大竹社長は「月100万円という販売目標には遠く及ばないが、リピーターは増えており、すでに30冊以上売れた児童書もある」と手応えを口にする。
返品率38・7%
書籍や雑誌は再販制度によって定価販売されている。これに対し、公正取引委員会は「消費者の利益を確保する」との理由から、業界に対して自由価格本の販売機会を広げるよう求めてきた。
こうした中、昭和図書では平成17年、東京・神田神保町に、絶版前の本などを半値で売る初の常設店「ブックハウス神保町」をオープン。今回のサイト開設と同様に、再販制度を弾力的に運用していることを積極的に打ち出すことで、制度そのものを死守する狙いがある。
また、大手出版社が系列を超えて値引きサイトに協力した背景には、高い返品率への危機感もある。出版科学研究所の調査によると、17年の書籍の返品率は38・7%。27〜30%程度で推移していた30年ほど前に比べ、増加が目立つ。昭和図書の大竹社長の推計では、年間約8億冊が返品され、うち2億冊が一度も読者の手に渡ることなく断裁処分されているという。販売部数が減る一方で新刊発行点数は年々増えており、返品率の上昇に拍車をかけているのが実態だ。
大竹社長は「ネットでの値引き販売は、在庫をいかにさばくかの方法を探る実証実験。著者のためにも、断裁処分を減らせるような流通システム作りにつなげていきたい」と話す。
出版業界は15年から、期間限定で自由価格本を販売する「謝恩価格本フェア」を開催している。10回目は4月23日〜6月23日、出版社112社が参加し、1473点の書籍が定価の5割引で販売される。詳細はバーゲンブック・jp(www.bargainbook.jp)。
産経新聞社から記事などのコンテンツ使用許諾を受けた(株)産経デジタルが運営しています。
すべての著作権は、産経新聞社に帰属します。(産業経済新聞社・産経・サンケイ)
Copyright(C)2008 SANKEI DIGITAL INC. All rights reserved.