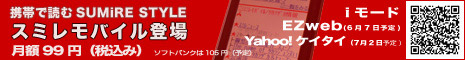「今の時代考えるきっかけに」
三宅一生に聞く「21世紀人」の未来は
2008/5/15
産経新聞東京朝刊 by 黒沢綾子
かつては異次元の未来に思えた21世紀に突入し、はや7、8年。テクノロジーの進歩を謳歌(おうか)する未来予想図はどこへやら、今、地球規模で「生命」にかかわる問題が切迫してきている。折しも「21世紀人」という名の展覧会が、東京ミッドタウン内の21_21デザインサイト(東京都港区)で開催中。果たして「21世紀人」に未来はあるのか。ディレクションを務めたデザイナー、三宅一生に聞いた。
「展覧会を見た人が、自分たちが生きている時代とはどういうものかを感じ、考えるきっかけにしてくれたら」と意図を語る。そのために結集したのは、国内外のアーティスト12組。それぞれの問題意識を出発点に、人間が乗り越えるためのアイデアやパワーを、デザインやアート作品に結実させた。
全体として「希望」が浮かび上がってくる展示の中で、核になっていると思われるのが、三宅自身とそのスタッフによるインスタレーション「21世紀の神話」だ。薄暗い空間に足を踏み入れた瞬間、ゾクッとする。
「恐怖を下敷きにしたおとぎ話です」と三宅。不気味に宙をうねる龍は、日本神話でおなじみ、8つの頭と尾を持つヤマタノオロチをイメージ。その中で舞い踊る8人の女は、ストラヴィンスキーのバレエ音楽「春の祭典」から着想したという。共通するのは、大地への畏怖(いふ)や礼賛、そして新しい生命への感謝。現代人が見失いがちなものを再認識させられる。
龍のトンネルを抜けて進むと、視界に等身大の男の裸体画が入ってくる。1930年、彫刻家のイサム・ノグチが北京滞在中に描いた墨絵「スタンディング・ヌード・ユース」だ。
米国人の母、日本人の父の間に生まれたノグチは当時26歳。この年、自身に流れる半分の血を求めて日本行きを決意するも、父に反対され、失意の中で行き先を北京に変える。そこで画家の斉白石に墨絵の技を学び、人間ばかり100点以上も描いたのだとか。
雄々しい男性の立ち姿からは、それでも人間を信じたいという、ノグチの切実な願いが感じられる。なぜ、三宅がこの作品を起点に展覧会を組み立てたのかもわかる。「デザインには希望がなければならない」というのが長年の持論だ。
「自分たちの時代はこんなに問題の多い時代なのかって、子供たちを怖がらせたくはない。人間には知恵があるし、美意識がある。エネルギーもある。それらをどう使うか。これから21世紀を生きる人々が、地球上でその命を全うすることを第一に考えなければ、と思うんです」

「展覧会を見た人が、自分たちが生きている時代とはどういうものかを感じ、考えるきっかけにしてくれたら」と意図を語る。そのために結集したのは、国内外のアーティスト12組。それぞれの問題意識を出発点に、人間が乗り越えるためのアイデアやパワーを、デザインやアート作品に結実させた。
全体として「希望」が浮かび上がってくる展示の中で、核になっていると思われるのが、三宅自身とそのスタッフによるインスタレーション「21世紀の神話」だ。薄暗い空間に足を踏み入れた瞬間、ゾクッとする。
「恐怖を下敷きにしたおとぎ話です」と三宅。不気味に宙をうねる龍は、日本神話でおなじみ、8つの頭と尾を持つヤマタノオロチをイメージ。その中で舞い踊る8人の女は、ストラヴィンスキーのバレエ音楽「春の祭典」から着想したという。共通するのは、大地への畏怖(いふ)や礼賛、そして新しい生命への感謝。現代人が見失いがちなものを再認識させられる。
龍のトンネルを抜けて進むと、視界に等身大の男の裸体画が入ってくる。1930年、彫刻家のイサム・ノグチが北京滞在中に描いた墨絵「スタンディング・ヌード・ユース」だ。
米国人の母、日本人の父の間に生まれたノグチは当時26歳。この年、自身に流れる半分の血を求めて日本行きを決意するも、父に反対され、失意の中で行き先を北京に変える。そこで画家の斉白石に墨絵の技を学び、人間ばかり100点以上も描いたのだとか。
雄々しい男性の立ち姿からは、それでも人間を信じたいという、ノグチの切実な願いが感じられる。なぜ、三宅がこの作品を起点に展覧会を組み立てたのかもわかる。「デザインには希望がなければならない」というのが長年の持論だ。
「自分たちの時代はこんなに問題の多い時代なのかって、子供たちを怖がらせたくはない。人間には知恵があるし、美意識がある。エネルギーもある。それらをどう使うか。これから21世紀を生きる人々が、地球上でその命を全うすることを第一に考えなければ、と思うんです」
産経新聞社から記事などのコンテンツ使用許諾を受けた(株)産経デジタルが運営しています。
すべての著作権は、産経新聞社に帰属します。(産業経済新聞社・産経・サンケイ)
Copyright(C)2008 SANKEI DIGITAL INC. All rights reserved.