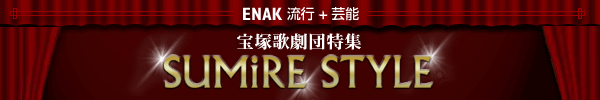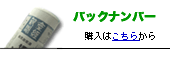|
|
日本舞踊の振付・指導 山村若:すみれの園を創る人たち
|
 |  |  |
|
舞踏会は古典をきっちりと
|
 |  |  |
日本舞踊を勉強しているタカラジェンヌたちの発表会が「宝塚舞踊会」。昭和28年に第1回が行われ、創立90周年の今年は第45回を数えて、29日午後4時から宝塚大劇場で実施される。
出演は専科の松本悠里、星組の湖月わたる他。90周年にちなみ、幕開きの「宝寿九重(たからづかいわうことぶき)秋錦繍(あききんしゅう)」で、箏曲「八千代獅子」を琴17面、三味線73丁の総勢90人で大演奏するのが話題だ。
その舞踊会の監修・指導をする1人が、上方舞山村流6世宗家の山村若さん。花柳流、藤間流に次ぐ流派として、第43回から参加している。
3度目の今回は、73人の三味線方の1人に、長男の侑(ゆう)くん(14)も初参加。父親が「ベルサイユのばら」などの演出家で前歌劇団理事長の植田紳爾さんだから、親子3代で宝塚の舞台にかかわることになる。
「舞踊会は邦楽の演奏で、古典をきちっとした形で舞う舞台。宝塚でしかできない山村流の作品はあると思うので、それらをさがして指導していきたい」という。
◆◆◆
昭和39年大阪生まれ。祖母が4世宗家で、早世した母に5世を追贈して、平成4年に6世を継ぎ、一門を率いている。文楽や歌舞伎の振付、宝塚音楽学校講師、New OSKの舞台なども担当。
山村流は江戸・天保年間に歌舞伎の振付師として認められた山村友五郎を流祖に、大阪で「地唄舞」「座敷舞」として発展。3世の初代山村若以来、女性によって伝えられてきた。6世は約100年ぶりの男性宗家になる。
宝塚で初めて振付を担当したのは、平成8年「CAN−CAN」での初舞台生口上。続いてバウの「冬物語」「花のいそぎ」など、大劇場の「源氏物語 あさきゆめみし」「花の宝塚風土記」などを手がけている。
「昔からの日舞は、まず歌詞があって踊りがある。洋楽で舞う宝塚の舞台は、音やリズムに数10人の振りを合わせる必要があるので、“順列組み合わせ”みたいな感覚ですね。宝塚は限りなくいろんなことができるのがすごいと思う」
|
 |  |  | 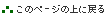 |  |  |  | | (C)2004.The Sankei Shimbun All rights reserved. |
|