 |
 |
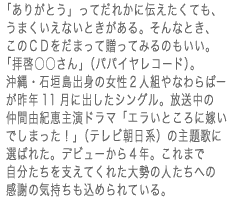 |
|
 |
|
ページ 1 | 2
||青い宝「よろしくお願いしまーす」と産経デジタルまで足を運んでくれた2人。飾り気のない印象は、そのまま2人の歌の世界に通じる。
「やなわらばー」。変わった名前。島の言葉で「やな」は「悪い」。「わらばー」は「わらべ」つまり子供。島では子供をしかるときに使うというから、愛情のこもった呼びかけの言葉なのだろう。
2人−−歌と三線の石垣優、歌とギターの東里梨生(あいざと・りお)−−は、「わらばー」のころからの友人。中高校が一緒。ともに小柄なせいか、大人びた級友たちからは「やなわらばー」と呼ばれることもあった。後にグループ名を決めるときに、この言葉が頭に浮かんだのはそのせい。今じゃ島の人たちから「そろそろ変えたら」と言われてしまうと苦笑い。
2人とも歌が大好きだったけれど、高校生のころは具体的に音楽活動をしていたわけではない。石垣が三線という沖縄独特の弦楽器を手にしたのは、高校で郷土の音楽に関するクラスを選択したからにすぎない。高校時代はついに弾けるようにはならなかった。
 それでも、そろって大阪の音楽専門学校に進学したのは、進路に迷い「歌が好き」をよすがにするほかなかったからなのだけど、振り返れば重要な決断だった。
それでも、そろって大阪の音楽専門学校に進学したのは、進路に迷い「歌が好き」をよすがにするほかなかったからなのだけど、振り返れば重要な決断だった。
大阪の専門学校で石垣は歌のクラス。東里は裏方を目指して音響のクラスを選んだ。大阪には石垣島出身者も大勢いるし風土もなじみやすい。先輩のひとことで出て行ったが、2人はなかなかなじめなかった。
「私たちにすれば電車に乗るどころか切符を買うことさえ初めてでした」と石垣は振り返る。言葉の違いにも悩まされた。親しい相手には「おまえよー」と話しかけるしまんちゅ(島人)。浪速っ子はまゆをひそめた。
遠慮が生じて級友とうまく話せなくなる。「休み時間になっても、うつむいて自分の席に座り続けていました」と石垣が続ける。
そんな2人の楽しみは週に1度、石垣か東里の部屋にしまんちゅの友人たちが集うときだけだった。
寂しさが募る。たまらずに学校の屋上に出た石垣は、大阪の空を見上げて、その空の向こうにあるふるさとに思いをはせた。島に帰りたい。旋律が生まれた。島の海は青かった。とても青かった。思いは言葉になり歌詞になった。
 石垣は、その思いと旋律を東里とともに歌に仕上げた。青い空を見てもっと青い海を思って生まれた旋律と歌詞は「青い宝」という歌になった。
石垣は、その思いと旋律を東里とともに歌に仕上げた。青い空を見てもっと青い海を思って生まれた旋律と歌詞は「青い宝」という歌になった。
2人は放課後の専門学校の廊下で「青い宝」をうたいながら形を整えた。残響効果が「どこのスタジオよりもよかった」と東里は笑う。くる日もくる日もその1曲だけをうたった。わらばーのころから一緒にうたっていたので自然にハーモニーをつけられた。
ある日、講師のひとりが声をかけた。2人のハーモニーはとてもいい。学校主催のオーディションに出なさい。もち歌1曲。しかも1年生で、そのオーディションに出た生徒はいなかったが、講師は強く勧めた。
石垣は寂しさをまぎらわせるために島から取り寄せた三線で、東里は大阪に出てから買った中古のギターで伴奏をつけた。オーディションが終わったとき、優勝者として読み上げられた名前は、2人が急ごしらえでつけた「やなわらばー」だった。
産経Webは、産経新聞社から記事などのコンテンツ使用許諾を受けた(株)産経デジタルが運営しています。
すべての著作権は、産経新聞社に帰属します。(産業経済新聞社・産経・サンケイ)
2007(C)SANKEI DIGITAL INC. All rights reserved.
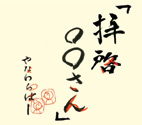 拝啓○○さん パパイヤレコード AKCY-58026 1,000円(税込)
●PROFILE やなわらばー 沖縄県石垣島育ちのおさななじみ同士。 ボーカルと三線(さんしん)担当の石垣優(左)、ボーカルとギター担当の東里梨生。 
家族と離れて暮らした寂しさを紛らわすために2人で曲を作ろうということになり、「青い宝」という曲を作った。 学校のオーディションで優勝し、さらに周りの人たちの応援でそのままユニットを組むことに。 2003年「変わらぬ『青』」でデビュー。 05年米ロスでライブ 06年、RYOJIプロデュースのシングル「唄の島」発売。 |
