
 |
|
|
| 劇作・演出家 柴田侑宏 | ||||
| 人間と男役の美学を描くのが使命 | ||||
「兄が監督で映画やテレビ、新劇には興味があったが、宝塚は見たことがなかったんです。実は民放テレビがスタートしたころで、いろいろなメディアに触覚も働いていた。宝塚は男役の存在が一番問題で、自分がやる世界なのかとも考えたけれど、芝居の仕事で給料をもらえるというのでお願いしました」という。 昭和33年3月、入団。3年目で早くもバウホール作品を手がける。 「自分の作品を見てもらえるという“蜜(みつ)の味”というか、ナイーブでクリエーティブな喜びを知ってしまった。それに古今東西の題材をこなせるのは宝塚だけ。同期に作曲家の寺田瀧雄(たきお)という朋友がいて、いい仲間に出会えたのも大きい。恵まれた時代でした」と振り返る。
宙(そら)組「白昼の稲妻」(関連記事:東京公演始まる)の主人公、アルベールは劇作家志望の青年だ。作者本人に重なる。
視力をなくし、平成10年の「黒い瞳」から演出を後輩に委ねるようになった。「白昼の稲妻」は若手の荻田浩一が演出。 「宝塚の舞台は本来、作と演出を分離しにくい仕事。自分が演出するのではない台本を書かなくてはいけない。ミュージカルナンバーの作りかた、構成の変更も演出家の仕事。当初はかなり苦しかった」 演出の意向でせりふをカットされることもある。しかし、せりふの重要性にはこだわり続けるという。 「『芝居はせりふ、せりふは言葉』です。劇作家は言葉を磨くことに執念を燃やすべき。“人間”が息づく舞台のために、せりふは本当に大事。そこに人間がいるんだという物語を、男役の美学とともに書くのが死ぬまでの私の命題です」
|
||||
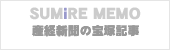 |
| 1月22日[木] by 田窪桜子 |
 |
| ●連載 産経新聞における主な宝塚関連連載記事は次のとおりです。 ・東京本社が発行する毎週木曜日朝刊の「SUMiRE STYLE」 ・大阪本社が発行する毎週月曜日夕刊の「The name of タカラジェンヌ」 ●番組表 東京版朝刊TVメディア面のBS・CS欄にはCSチャンネル「TAKARAZUKA SKY STAGE」の番組表と解説を毎日掲載しています。 ●OG関連記事 演劇一般など、それぞれ活動のジャンルごとに掲載しています。 |
| ●ENAK編集部 ●編集局文化部 |

